学術システム研究センター
Research Center for Science SystemsPOからのメッセージ
学術システム研究センター研究員の経験者から
- 応募者や審査員とは異なる視点から、科研費や特別研究員事業等の理解を深めることができた!
- 科研費や特別研究員事業等の根幹を支えることに貢献できたとの思いがある!
- この業務がなければ知り合えなかった異分野研究者との交流ができた!
- 自らの専門性を活かしつつ、幅広い視野で学術研究を捉えられるようになった!
- 我が国の学術研究の発展に貢献している実感が芽生えた!
という感想が寄せられています
執筆者の所属班、所属機関、事業名等の記載内容については、執筆当時のものとなっています。
科研費改革2018を通して学んだこと

尾辻 泰一
東北大学
電気通信研究所教授
学術システム研究センター参与(令和4年4月~)
特命事項担当(科研費改革推進等)主任研究員(平成31年4月~令和4年3月)
工学系科学専門調査班主任研究員(平成27年4月~平成31年3月)
電気通信研究所教授
学術システム研究センター参与(令和4年4月~)
特命事項担当(科研費改革推進等)主任研究員(平成31年4月~令和4年3月)
工学系科学専門調査班主任研究員(平成27年4月~平成31年3月)
2017年4月に工学班主任研究員として着任したのがRCSSとのご縁の始まりでした。以来、 4年間の工学班主任研究員、続く3年間の特命事項担当を経て、現在は参与として2年目を迎えています。9年間にわたるRCSSでの経験と人脈は、私の人生においてかけがえのない宝物となりました。その経験の中でも、科研費改革2018は自身がセンターの一員として全霊を賭して取り組ませていただいた一大事業でした。「学びてその先に『問い』は生まれる。科研費は『新たに生まれた問い』に対する支援制度である」この言葉に科研費改革2018の精神が象徴されていると思います。新たな課題の発見に始まり、その課題に対して合理的かつ革新的な手段で見えない答えを自ら導き出し発見すること、それをScientific meritとして尊び、評価すること。ここに審査方式改革の理念が凝集されていると思います。RCSS入所当時に今は亡き初代副所長の石井紫郎先生の言葉として、当時副所長であった勝木先生より訓示いただいた「センター研究員は、歯がゆいほどに我慢強く、謙虚であるべき」という金言を鏡として、不断の改革に微力ながら尽くして参りたいと存じます。
(2023年度RCSSパンフレットに掲載。)
楽しく実りある研究員生活

大川 剛直
神戸大学大学院
システム情報学研究科教授
情報学専門調査班主任研究員(令和2年4月~令和6年3月)
システム情報学研究科教授
情報学専門調査班主任研究員(令和2年4月~令和6年3月)
学術システム研究センターの主任研究員に就任して、 3年余りが過ぎました。研究員の業務はウェブページ等でも紹介されているように非常に多岐にわたっていますが、中でも科研費審査会への陪席は、私にとって最も興味深いものでした。分野によって学術研究に対する価値観や捉え方が根本的に異なることに戸惑いを覚えつつも、審査委員の方々の学術にかける真摯な想いをまざまざと感じることができました。また、様々な分野における最先端で挑戦的な研究内容をつまみ食いできる非常に楽しい時間でもあり、もともと自分の専門とは異なる分野に関心が行きがちな浮気性の私にとっては、思わぬ役得に心躍りました。
一方、科研費WGの主査として、「科研費の審査の在り方」について議論させていただいたことも、大変有意義な経験となりました。これまであまり顧みることのなかった科研費の精神の真髄を垣間見ることができ、科研費制度が健全に運営され、継続的な改善がなされているのは、学術システム研究センターでの議論もさることながら、学振事務局の皆様のプロフェッショナルな仕事の賜物であることを肌で感じさせてもらいました。心から感謝申し上げたいと思います。
この3年間、本当に楽しく実りある研究員生活で、残すところ数ヶ月となったことを少し寂しく感じています。
一方、科研費WGの主査として、「科研費の審査の在り方」について議論させていただいたことも、大変有意義な経験となりました。これまであまり顧みることのなかった科研費の精神の真髄を垣間見ることができ、科研費制度が健全に運営され、継続的な改善がなされているのは、学術システム研究センターでの議論もさることながら、学振事務局の皆様のプロフェッショナルな仕事の賜物であることを肌で感じさせてもらいました。心から感謝申し上げたいと思います。
この3年間、本当に楽しく実りある研究員生活で、残すところ数ヶ月となったことを少し寂しく感じています。
(2023年度RCSSパンフレットに掲載。)
協働が織りなすシステム運営の妙

川口 裕司
東京外国語大学名誉教授
人文学専門調査班主任研究員(平成31年4月~令和5年3月)
人文学専門調査班主任研究員(平成31年4月~令和5年3月)
フランス語にはC'est en forgeant qu'on devient forgeron.「鉄を鍛えることで鍛冶屋になる」ということわざがある。センター研究員にとっては、科学研究費補助金制度と若手研究者の育成システムをどのように鍛え上げ洗練していくか、それが主たる任務である。鍛冶屋の職能が他の人に言葉でうまく伝えることができないのと同じように、センター研究員の仕事も経験を積み上げていくことで徐々に身についてゆく。とはいえ、新たに弟子入りした新米研究員には頼りになる親方がいなくてはならない。だが心配には及ばない。学術振興会にはたくさんの優れた玄人たちがいる。主任研究員が何なのかを理解しないまま始めた私のような者でも、3年間の任期がコロナ感染症のために1年延びてしまっても、つつがなく職務を全うすることができた(これは個人的な感想だ!)のは、センター研究員と作業テーマごとに綿密に配置された担当者との協働作業によるシステム運営があったからだと思う。この点はこれからセンター研究員になられる方々も安心してほしい。思えば私は頻繁に学振の方に質問をしていたが、それができたのも学術振興会が気軽にコミュニケーションをとることができる雰囲気作りに成功していたからなのだろう。
(2023年度RCSSパンフレットに掲載。)
学術システムセンターの調査研究活動について
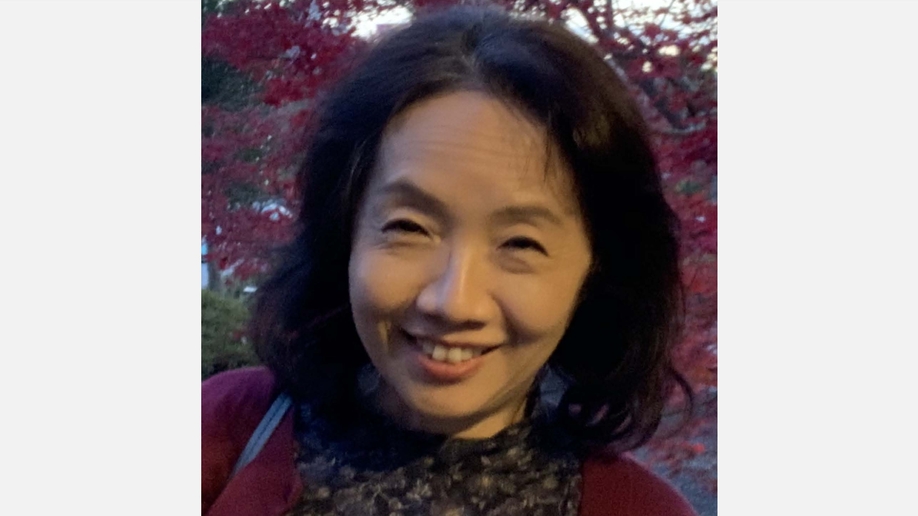
平田 たつみ
国立遺伝学研究所
脳機能研究室教授
生物系科学専門調査班専門研究員(平成31年4月~令和5年3月)
脳機能研究室教授
生物系科学専門調査班専門研究員(平成31年4月~令和5年3月)
学術システム研究センター研究員として働いた経験は、私にとって楽しく有意義なものでした。科研費のしくみをより深く理解することができましたし、研究現場にどのような問題があるのかを知ることができました。好奇心が強い私にとって、多くの予想外の発見がありました。また様々な分野の研究員と知り合うことができたことも、とても有益でした。これらの経験は今後の財産になると確信しています。
以上に加えて、毎年学術システムセンターの研究員として学術動向調査研究の報告ができる機会をいただけたことにとても感謝しています。日々様々なことに興味をもって生活する研究者として、この機会を存分に利用して、毎年全く異なるトピックについて調査報告させていただきました。公式に調査できるお墨付きをいただける上に、自分の意見を自由に発信できる機会をいただけるのですから、大変光栄なことであったと感じています。せっかくの調査結果をもう少し幅広く皆さんに届けたいという願いもありますが、毎年異なる研究関係者から反響をもらうことができて、この調査を通じて研究者の視点をある程度発信することができたと思っています。
以上に加えて、毎年学術システムセンターの研究員として学術動向調査研究の報告ができる機会をいただけたことにとても感謝しています。日々様々なことに興味をもって生活する研究者として、この機会を存分に利用して、毎年全く異なるトピックについて調査報告させていただきました。公式に調査できるお墨付きをいただける上に、自分の意見を自由に発信できる機会をいただけるのですから、大変光栄なことであったと感じています。せっかくの調査結果をもう少し幅広く皆さんに届けたいという願いもありますが、毎年異なる研究関係者から反響をもらうことができて、この調査を通じて研究者の視点をある程度発信することができたと思っています。
(2023年度RCSSパンフレットに掲載。)
科研費制度を未来につなげるために

竹山 春子
早稲田大学大学院
先進理工学研究科教授
農学・環境学専門調査班主任研究員(平成31年4月~令和5年3月)
先進理工学研究科教授
農学・環境学専門調査班主任研究員(平成31年4月~令和5年3月)
歴史に残る新型コロナパンデミックが始まる1年前に農学・環境班の主任研究員を務めることになりました。専門研究員の経験もないところでのスタートだったこともあり、同じ主任の先生方、センターの方々には非常にお世話になりました。センターの業務を知るにあたっては、驚きとともに多くの先生方の真摯な働きによって科研費制度が成り立っていることが良くわかりました。コロナ禍ですべての会議はオンラインとなり、先生方との交流が限定的となってしまい本当に残念でした。コロナ禍が続いたこともあり、研究員の任期が1年延びて2023年3月までの4年間となりました。その中で、一番印象に残ったことは最後の2年間、特別研究員ワーキングの副主査、主査を務めたことです。特別研究員制度は日本の若手研究者、博士課程の学生にとっては非常に重要なものであり、今後の研究力の担い手の育成には欠かせないものです。一方、制度ができて以来その中身が時代に対応しきれておらず課題の解決がなされないままでした。特に特別研究員(PD)の非雇用状態に関する問題点を中心にWGで討議を始め、センター、文部科学省の英断で、PDが研究をする機関での雇用が可能になる制度がつくられました。
センター研究員は、科研費の採択業務だけでなく制度設計に関しても踏み込んで意見を戦わせ、研究者環境の向上に資することも科研費制度を未来につなげるために必要であると強く感じた4年間でした。
センター研究員は、科研費の採択業務だけでなく制度設計に関しても踏み込んで意見を戦わせ、研究者環境の向上に資することも科研費制度を未来につなげるために必要であると強く感じた4年間でした。
(2023年度RCSSパンフレットに掲載。)
研究環境の整備

井関 祥子
東京医科歯科大学大学院
医歯学総合研究科教授
医歯薬学専門調査班専門研究員(平成30年4月~令和4年3月)
医歯学総合研究科教授
医歯薬学専門調査班専門研究員(平成30年4月~令和4年3月)
センター研究員を務める前、この仕事を認識していたものの、どのような業務であるか知らずにいました。研究員として日本学術振興会の様々な事業に関与し、この業務が、研究の多様性を維持し、研究者がよりよい研究活動をすることのできる環境を最大限公平に提供する事務方とのコラボレーションであり、やりがいのあるものだと認識できました。
私は医歯薬学班の所属で、月一度の班会議ではこの領域の最新の学術動向を知ることができ、また、業務をしている中で他の研究領域の動向を知る機会もありました。このように、研究環境に貢献するだけでなく自身の学びにもなり、有意義な時間でした。業務に大きな割合を占めるのは、やはり科研費業務です。科研費は研究者の自由な発想による研究を支援するもので、これが日本の学術を支える研究費であると考えると、時代に合わせながらのより良い科研費システムの整備に微力ながら貢献できたことに感謝しています。
任期2年目で新型コロナ感染拡大が起き、班会議がオンラインになりました。出席率は上がるのですが、対面でないため、他の研究員の先生方との関係が希薄になってしまったのは少し残念でした。今後も機会があればこの経験を生かしたいと考えています。
私は医歯薬学班の所属で、月一度の班会議ではこの領域の最新の学術動向を知ることができ、また、業務をしている中で他の研究領域の動向を知る機会もありました。このように、研究環境に貢献するだけでなく自身の学びにもなり、有意義な時間でした。業務に大きな割合を占めるのは、やはり科研費業務です。科研費は研究者の自由な発想による研究を支援するもので、これが日本の学術を支える研究費であると考えると、時代に合わせながらのより良い科研費システムの整備に微力ながら貢献できたことに感謝しています。
任期2年目で新型コロナ感染拡大が起き、班会議がオンラインになりました。出席率は上がるのですが、対面でないため、他の研究員の先生方との関係が希薄になってしまったのは少し残念でした。今後も機会があればこの経験を生かしたいと考えています。
(2023年度RCSSパンフレットに掲載。)
科学の健全な発展に貢献するコミュニティの一員となる喜び

今井 小の実
関西学院大学人間福祉学部
社会福祉学科教授
社会科学専門調査班専門研究員(平成29年4月~令和2年3月)
社会福祉学科教授
社会科学専門調査班専門研究員(平成29年4月~令和2年3月)
「たとえ何度同じ運命を辿ることになっても、私はまた同じ選択をする」。正確な表現は忘れたが、今も人気を誇る韓国ドラマの中の、生死を彷徨うヒロインが口にした譫言である。専門研究員の仕事はかなり過酷だ。けれども私も何度同じ運命を辿ることになっても、この仕事を引き受けるだろう。なぜなら、ここでの経験と出会いが何物にも代え難いものだったからだ。選考と検証、学術振興会賞候補の選定、制度への提言など、当初は理解が及ばず、異世界に迷い込んだかのような孤独に陥った。けれどもスタッフや同志の先生方の存在によって乗り越えることができた。そして今まで研究費を獲得するための手段としか思っていなかった科研費の制度が、公正で適切な運営のために、専門家と職員と研究者の不断の努力によって守られてきたことを知った。決して楽ではない行程に学術研究の発展を支える矜持と誇りを感じ、研究者として使命感を持って臨んできた。人文・社会班で開催される定例会の前の研究会で、各分野で活躍される先生方の研究に触れた時のワクワク感は忘れられない。業務と懇親会で培った人間関係は今も大切な財産だ。健全な科学の発展に貢献するコミュニティへの参加、その喜びと得難い仲間との出会いに感謝する。
(2023年度RCSSパンフレットに掲載。)
スーツを着てセンターへ

小島 定吉
東京工業大学名誉教授
数物系科学専門調査班主任研究員(平成28年4月~令和2年3月)
数物系科学専門調査班主任研究員(平成28年4月~令和2年3月)
主任研究員の務めを終えてからすでに3年4ヶ月が経ち、RCSSの様子もだいぶ変わったと推察します。以下は思い出話になってしまいますが、ご容赦ください。
4年間務めましたが、普段ジャケットすら着ることがない私のスーツ着用率は、フォーマルな場のみで年間1%に満ちませんが、この期間だけは平均5日/1ヶ月 = 17%と異常な比率となり、それなりに背筋を正す機会となりました。スーツ&タイが義務付けられているわけではありませんが、周りに倣い自らドレスコードを設定しました。それに見合う恩恵は、一つは科研費や特別研究員事業の行政現場に触れられたこと、今一つはハイレベルの役員・研究員の皆さまと交流ができたことがあります。いずれも締まった服装で臨み充実した経験をさせていただきました。コロナが始まった2020年3月に誠に残念ながら送別会なしで退任しスーツ着用率年間1%以下の生活に戻りましたが、なぜか気分は一新し、楽しい4年間だったと感慨深く思っています。
4年間務めましたが、普段ジャケットすら着ることがない私のスーツ着用率は、フォーマルな場のみで年間1%に満ちませんが、この期間だけは平均5日/1ヶ月 = 17%と異常な比率となり、それなりに背筋を正す機会となりました。スーツ&タイが義務付けられているわけではありませんが、周りに倣い自らドレスコードを設定しました。それに見合う恩恵は、一つは科研費や特別研究員事業の行政現場に触れられたこと、今一つはハイレベルの役員・研究員の皆さまと交流ができたことがあります。いずれも締まった服装で臨み充実した経験をさせていただきました。コロナが始まった2020年3月に誠に残念ながら送別会なしで退任しスーツ着用率年間1%以下の生活に戻りましたが、なぜか気分は一新し、楽しい4年間だったと感慨深く思っています。
(2023年度RCSSパンフレットに掲載。)
扉の向こう側
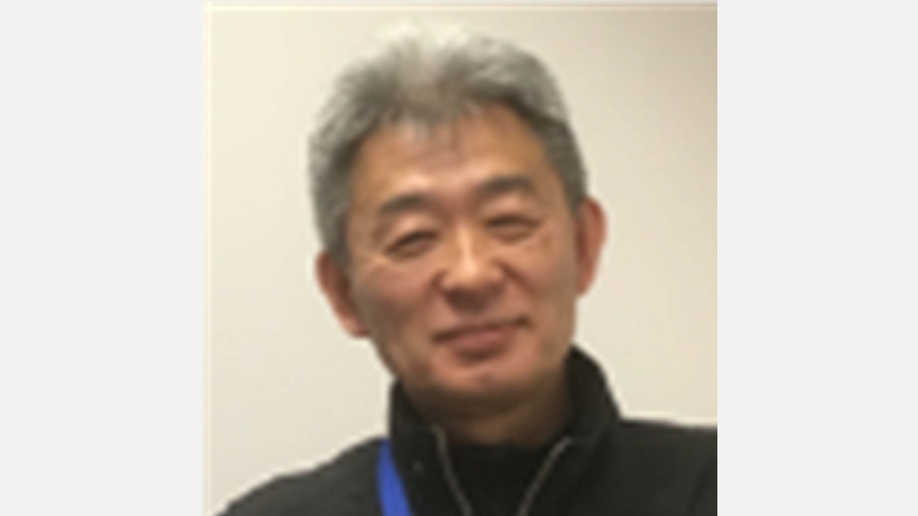
杉山 純
一般財団法人総合科学研究機構
中性子科学センター・サイエンスコーディネータ
工学系科学専門調査班専門研究員(平成28年4月~平成31年3月)
中性子科学センター・サイエンスコーディネータ
工学系科学専門調査班専門研究員(平成28年4月~平成31年3月)
私が学術システム研究センターの専門研究員を終了したのは2019年3月末でした。と同時に、私企業である研究所会社から(一財)総合科学研究機構(CROSS)へ転職しました。CROSSは共用法に基づきJ-PARCの中性子散乱装置の共用促進を担う組織なので、私企業時代より科研費は身近になりました。そのような自分自身の環境の変化も合わせて、センター研究員時代を回顧します。まず科研費申請書類の審査過程をかなり詳細に追跡することに驚きました。次いで審査委員の選考の際に、不適切な選考とならないように配慮されていることに感心しました。さらに合議審査会への陪席を通して、審査の実状を目の当たりにしました。当時の学振理事の言われた「採択される申請書の書き方は分からないが、採択に至らない場合の理由を理解できます。」は名言でした。CROSS転職後もセンター研究員時代の経験は、国内外の大型施設の実験提案審査や研究予算審査で大変役立っています。科研費審査の公平性を保つためのセンター研究員の各種活動は、審査員を育成するシステムとなっていると言うことでしょうか。
(2023年度RCSSパンフレットに掲載。)
学術の多様性を支える科研費

森 初果
東京大学物性研究所
凝縮系物性研究部門教授
東京大学副学長
化学専門調査班専門研究員
(平成27年4月~平成30年3月)
凝縮系物性研究部門教授
東京大学副学長
化学専門調査班専門研究員
(平成27年4月~平成30年3月)
学術の原点はあくなき好奇心であり、個人が提案する基盤研究から、横断型の学術変革のようなグループ研究まで、多様な学術分野の研究を支えているのが科研費で、我々研究者の命綱であります。その科研費が、正当かつ公平な評価で配分されるよう、我々研究者が、学術システム研究センターの運営に参画させていただいたのはとても貴重な経験でした。さらに、日本学術振興会におけるシンクタンクとして、学術の発展を鑑みて5年に1度、分野やキーワードを見直したり、現場目線で科研費システムに意見を述べる機会もあり、研究者の思いを伝えられる重要な組織であることを専門研究員になって初めて知りました。
センターの研究員だったのはコロナ前でしたので、会議は基本対面で、研究業務もセンター内で行っておりました。運営業務に追われる中でも毎月楽しみだったのは、研究員の先生から他分野の最先端の研究発表を伺い、そのあと四ツ谷での懇親会で多様な分野の先生方と四方山話ができたことです。今も、その時ご一緒だった先生方とは交流させていただいており、人との繋がりの機会をいただいたのも財産だったと感じております。
センターの研究員だったのはコロナ前でしたので、会議は基本対面で、研究業務もセンター内で行っておりました。運営業務に追われる中でも毎月楽しみだったのは、研究員の先生から他分野の最先端の研究発表を伺い、そのあと四ツ谷での懇親会で多様な分野の先生方と四方山話ができたことです。今も、その時ご一緒だった先生方とは交流させていただいており、人との繋がりの機会をいただいたのも財産だったと感じております。
(2023年度RCSSパンフレットに掲載。)
対面できることの価値

松井 知子
情報・システム研究機構
統計数理研究所教授
情報学専門調査班専門研究員(平成30年4月~令和4年3月)
総合系専門調査班専門研究員(平成24年4月~平成27年3月)
統計数理研究所教授
情報学専門調査班専門研究員(平成30年4月~令和4年3月)
総合系専門調査班専門研究員(平成24年4月~平成27年3月)
4年間の専門研究員の任期のうち、後半の2年間はコロナ禍のため、オンラインでの会議が続きました。有り体に言えば、後半の2年間はもったいない思いでした。
専門研究員になり、一番有益だったのは他の研究員の先生方と知り合えたことです。皆それぞれの学術的専門性に加え、何より人間性に優れておられます。対面可能な時期に班会議、および懇親会で科研費制度や科学技術のあり方について真剣に議論を交わせたことは貴重な経験でした。特に懇親会は班を跨って議論する機会もあり、分野の垣根を超えた刺激を受けました。科研費制度が研究員の先生方、それを支える学術システム研究センターの方々による真摯な取り組みの上に構築され、問題があれば改善されていく様子を間近に目にすることができました。
心残りは、科研費の審査区分表で情報学、数物系科学、社会科学にまたがっている統計科学(自分の専門の一つ)について、大幅な見直しを行う前に任期が終わることです。今後はこの件を含め、科研費制度に関して、センター研究員経験者として前向きに意見していけたらと考えています。
最後に、この4年間、大変お世話になりました情報学班の皆様、センターの皆様に深く御礼申し上げます。
専門研究員になり、一番有益だったのは他の研究員の先生方と知り合えたことです。皆それぞれの学術的専門性に加え、何より人間性に優れておられます。対面可能な時期に班会議、および懇親会で科研費制度や科学技術のあり方について真剣に議論を交わせたことは貴重な経験でした。特に懇親会は班を跨って議論する機会もあり、分野の垣根を超えた刺激を受けました。科研費制度が研究員の先生方、それを支える学術システム研究センターの方々による真摯な取り組みの上に構築され、問題があれば改善されていく様子を間近に目にすることができました。
心残りは、科研費の審査区分表で情報学、数物系科学、社会科学にまたがっている統計科学(自分の専門の一つ)について、大幅な見直しを行う前に任期が終わることです。今後はこの件を含め、科研費制度に関して、センター研究員経験者として前向きに意見していけたらと考えています。
最後に、この4年間、大変お世話になりました情報学班の皆様、センターの皆様に深く御礼申し上げます。
(2022年1月執筆、2022年2月掲載。)
ピア・レビューの苦労と喜び

神田 展行
大阪市立大学大学院
理学研究科教授
数物系科学専門調査班主任研究員(平成31年4月~令和4年3月)
数物系科学専門調査班専門研究員(平成30年4月~平成31年3月)
理学研究科教授
数物系科学専門調査班主任研究員(平成31年4月~令和4年3月)
数物系科学専門調査班専門研究員(平成30年4月~平成31年3月)
科研費制度に恩返しと思ってセンター研究員を引き受けた。毎年10万件以上の申請を滞りなく処理している優秀な事務局を目の当たりにし、漠然と思っていた以上に研究者が支えられていることを実感した。科研費審査はピア・レビュー方式であるから、研究者自身も直接に制度貢献している。冬休みをすっかり潰してしまう書面審査件数や大型科研費の複数回の審査会などにもかかわらず、多くの審査委員が粛々と貢献してくださっていることにもこの機会にお礼を述べたい。応募するほうも様式書類などで手間がかかっている。
だが、センター研究員の仕事をしながら、私は少し違う考えもするようになった。研究者たる我々が、大変だ、苦労する、ばかりをぼやいているのは情けなくないか?苦役のように思う科学者に税金を使うことは社会も了解しないだろう…。そう考えていたところ、大変ではあったが勉強になったという審査委員の感想を何度か聞いて勇気づけられた。
さらにもう一歩進めて、応募も審査も、もっと前向きに楽しんだら良いのではないか。そもそも、自分の研究を誰かに語るのも、多くの研究提案を知るのも、科学者の喜びであるはずだ。「楽しい科研費応募!」が次の目標である。
だが、センター研究員の仕事をしながら、私は少し違う考えもするようになった。研究者たる我々が、大変だ、苦労する、ばかりをぼやいているのは情けなくないか?苦役のように思う科学者に税金を使うことは社会も了解しないだろう…。そう考えていたところ、大変ではあったが勉強になったという審査委員の感想を何度か聞いて勇気づけられた。
さらにもう一歩進めて、応募も審査も、もっと前向きに楽しんだら良いのではないか。そもそも、自分の研究を誰かに語るのも、多くの研究提案を知るのも、科学者の喜びであるはずだ。「楽しい科研費応募!」が次の目標である。
(2021年10月執筆、掲載。)
縁の下の力持ち

野村 眞理
金沢大学
人間社会研究域教授
人文学専門調査班主任研究員(平成28年4月~令和2年3月)
人間社会研究域教授
人文学専門調査班主任研究員(平成28年4月~令和2年3月)
学術システム研究センター? 何、それ?
いまどき「学振」や「科研費」を知らなければ、研究者としては潜りを疑われても仕方がない。それが「学術システム研究センター」となると、話は別である。何を隠そう私自身「何、それ?」の1人だった。だが考えてみれば、科研費の存続には、その制度を設計、改革し、審査員を選び、審査結果を検証する組織の存在もまた不可欠である。
学術システム研究センターは、科研費のみならず、特別研究員制度や国際学術交流、学術振興会賞、育志賞の査読など、学振が行うほとんどすべての事業にかかわり、業務は多忙を極める。主任研究員の場合、センターへの出張は年間30数回に及ぶだろう。しかも「何、それ?」のセンター研究員の仕事は、研究上の評価を受けることもなければ、表だって感謝されることもない。しかし、センターの各種会議に出席して私が感動し、尊敬すら感じたのは、所長、副所長以下、研究員全員が日本の学術研究を支える縁の下の力持ちであることに使命感を見出し、非常に仕事熱心なことだ。私もまたこれまでセンターの仕事に携わられた先輩方に続き、微力ながらも課せられた使命をはたしたいと思う。
いまどき「学振」や「科研費」を知らなければ、研究者としては潜りを疑われても仕方がない。それが「学術システム研究センター」となると、話は別である。何を隠そう私自身「何、それ?」の1人だった。だが考えてみれば、科研費の存続には、その制度を設計、改革し、審査員を選び、審査結果を検証する組織の存在もまた不可欠である。
学術システム研究センターは、科研費のみならず、特別研究員制度や国際学術交流、学術振興会賞、育志賞の査読など、学振が行うほとんどすべての事業にかかわり、業務は多忙を極める。主任研究員の場合、センターへの出張は年間30数回に及ぶだろう。しかも「何、それ?」のセンター研究員の仕事は、研究上の評価を受けることもなければ、表だって感謝されることもない。しかし、センターの各種会議に出席して私が感動し、尊敬すら感じたのは、所長、副所長以下、研究員全員が日本の学術研究を支える縁の下の力持ちであることに使命感を見出し、非常に仕事熱心なことだ。私もまたこれまでセンターの仕事に携わられた先輩方に続き、微力ながらも課せられた使命をはたしたいと思う。
(『学術システム研究センターリーフレット2017』2017年4月より)
主任研究員の仕事

仲 真紀子
北海道大学大学院
文学研究科教授
社会科学専門調査班主任研究員(平成27年4月~平成30年3月)
文学研究科教授
社会科学専門調査班主任研究員(平成27年4月~平成30年3月)
日本学術振興会といえば、科研費や幾多の研究経費でたいへんお世話になっているところである。この中に学術システム研究センターというのがあり、所長役員のもと主任研究員、専門研究員という方々が科研費等の公正な審査・評価に拘る業務に携わっておられる…と他人事のように書いたが、昨年4月から私にもこの仕事が回ってきた。HPにもあるように、主任研究員は人文、社会科学、数物、化、工、生物等々の異なる分野から基本各2人、計20人。原則3年任期である。社会科学にも法、経済、社会等いろいろあるが、各分野の2人は異なる領域、かつ前任者と後任者も異なる領域でなければならず、心理(私の領域)の主任研究員も10年に1度ということになるのだろうか。科研費、特推、特設、特研、海特、学振賞(略語が多い)等につき隔週朝~夕の会議の他振興会内でのみ可能な業務、審査、陪席は、北海道からの身としては大変である。しかし、主任研究員会議は異分野他領域が交差するギャラクシー宇宙ステーションのようでもあり、発見・感銘というエネルギー補給の場となっている。科研費申請書を書かれるとき、裏方にこのような場所があることを少しだけ想像してみて頂ければ幸いである。
(『学術システム研究センターリーフレット2016』2016年4月より)
裏方に徹する

八島 栄次
名古屋大学大学院
工学研究科教授
化学専門調査班主任研究員(平成27年4月~平成30年3月)
工学研究科教授
化学専門調査班主任研究員(平成27年4月~平成30年3月)
科研費を申請し、その結果に一喜一憂しつつ、分厚い研究計画調書の審査も当然の仕事と思いやってきましたが、この一連の審査システムに思いを馳せたことはなく、我々と同じ現役の研究者が携わっていることを本センターの主任研究員になって初めて知りました。粛々と型通りの業務を淡々とするのかと思いきや、個性溢れる(強者揃いの)研究者・執行部の方々とこのみちのプロであるセンター職員が、審査・評価システムの改善と新たな科研費の提案・審査システムの改革に向けて、白熱した議論を闘わせています。予算には限りがあり、出来ることにも限界があることは承知の上で、学術の根幹を支える我々研究者のための研究費であるという確固たる信念を崩さず、裏方に徹する姿勢には感銘を覚えました。慣れない仕事が多く、つい愚痴もこぼれそうになりますが、「回りから大変だと思われないよう、さらっとカッコ良く、完璧にやりましょう」と言われ、また愕然....でも、これが出来る方々が本当に居られ、世の中が広いことも実感しました。2年が経ち、漸くセンターの仕事にも慣れ、愛着とやり甲斐も感じつつあります。危険な兆候です。ただ、この仕事をしなかったら出会うこともなかった異分野の方々との雑談は結構楽しく、残り1年乗り切る気力が沸いてきます。
(『学術システム研究センターリーフレット2017』2017年4月より)
専門研究員としての誇りと責任

中西 晶
明治大学
経営学部教授
社会科学専門調査班専門研究員(平成27年4月~平成30年3月)
経営学部教授
社会科学専門調査班専門研究員(平成27年4月~平成30年3月)
学術システム研究センターとは何か。所属機関から推薦の打診があったとき、正直、どのような業務であるのか想像がつかず、Webサイトで検索をした。その結果、科研費に関する非常に重要な業務を担っていることを理解した。しかも、ちょうど科研費改革についての議論が佳境で、学問のカテゴライゼーションやディシプリンについても深く考えるきっかけとなった。すべての研究者のニーズを満たすことは難しいが、事務局も含めて、多くの人々がよりよい方向を目指して真摯に検討した成果だということは間違いない。私自身も科研費の恩恵を受けている人間として、大切に使っていきたいと思う。
月一回の人文学班と社会科学班の合同班会議は、楽しみの一つである。全国から集まる専門研究員の方々との議論や情報交換の中で、多くの発見があった。また、特設研究分野や複合領域関係の業務においては、医学や工学など他分野の最先端の研究を知ることができるという「役得」もある。時には、長時間の会議などもあり、ハードな仕事であるが、それはピアレビューを徹底し、議論を尽くしている証拠である。これからも科研費が日本の研究活動の基盤を支えていくことは明らかであり、その活動に専門研究員として微力ながらも貢献できることは大きな誇りであり、責任を感じている。
月一回の人文学班と社会科学班の合同班会議は、楽しみの一つである。全国から集まる専門研究員の方々との議論や情報交換の中で、多くの発見があった。また、特設研究分野や複合領域関係の業務においては、医学や工学など他分野の最先端の研究を知ることができるという「役得」もある。時には、長時間の会議などもあり、ハードな仕事であるが、それはピアレビューを徹底し、議論を尽くしている証拠である。これからも科研費が日本の研究活動の基盤を支えていくことは明らかであり、その活動に専門研究員として微力ながらも貢献できることは大きな誇りであり、責任を感じている。
(『学術システム研究センターリーフレット2017』2017年4月より)
日本の学術研究力は

田中 純子
広島大学大学院
医歯薬保健学研究院教授
医歯薬学専門調査班専門研究員(平成27年4月~平成31年3月)
医歯薬保健学研究院教授
医歯薬学専門調査班専門研究員(平成27年4月~平成31年3月)
学術システム研究センター専門研究員を拝命し、研究道への切符ともいえる科学研究費助成事業に関わる業務、日本の研究・研究者を支える国内外を通じた様々な国際交流事業、社会との連携事業や人材育成事業の一部を知る機会を得て2年が経過しました。私の属する医歯薬班の会議に参集される専門研究員の先生方は、基礎医学・臨床医学・社会医学・薬学・歯学・保健学と分野も個性も大きく異なり、時には意見が対立することもあります。それでも会議での凛とした空気は、公平性と正確性そして創造性を強く求められている上記業務の一部を担っているとの一貫した見識から自然と生まれていると感じています。
私はまた、組織としての研究センターの必要性を感じています。特に、近未来だけでなく将来の研究・学術を支える人材を育成する組織という意味において、毎年学術動向を探り、既存の研究分野や分科細目にこだわらず、「挑戦的」「萌芽」「開拓」や「特設」という言葉が示すように、時代を先取りしているがまだ小さな研究分野、シーズを見落とさないようセンター全体が真摯に取り組んでいます。センターの業務は膨大で煩雑で、多くの人の多くの時間がかけられていますが、日本の将来の研究力を地道に力強く公正に支えている組織なのだと認識できたことに、一研究者として感謝しています。
私はまた、組織としての研究センターの必要性を感じています。特に、近未来だけでなく将来の研究・学術を支える人材を育成する組織という意味において、毎年学術動向を探り、既存の研究分野や分科細目にこだわらず、「挑戦的」「萌芽」「開拓」や「特設」という言葉が示すように、時代を先取りしているがまだ小さな研究分野、シーズを見落とさないようセンター全体が真摯に取り組んでいます。センターの業務は膨大で煩雑で、多くの人の多くの時間がかけられていますが、日本の将来の研究力を地道に力強く公正に支えている組織なのだと認識できたことに、一研究者として感謝しています。
(『学術システム研究センターリーフレット2017』2017年4月より)
専門研究員を経験して学んだこと

喜々津 哲
(株)東芝 研究開発センター
スピンデバイスラボラトリー研究主幹
総合系専門調査班専門研究員(平成26年4月~平成29年3月)
スピンデバイスラボラトリー研究主幹
総合系専門調査班専門研究員(平成26年4月~平成29年3月)
私は企業の研究者で科研費とはあまり縁がなく、科研費の種類もよくわからないまま専門研究員の業務に携わることになりました。そこで初めて審査員の先生方の評価結果を拝見したのですが、それは、膨大な件数の応募書類を読み込み、ひとつひとつに評価結果とコメントを書きこんだ書類の大きな束でした。その束の大きさに圧倒されながらも、今まであまり認識していなかったけれども、これだけ多くの人々が携わって初めてピアレビューの仕組みが保てるのだということを改めて学びました。
ここで学んだものは科研費のことだけではありません。私の所属した工学/総合班には、工学とその境界領域の各分野で日本を代表する先生方が集まっておられます。毎月の会議で先生方からそれぞれの分野の最先端の話を聞かせていただけるのですが、これが初めて聞く刺激的なものばかりで、企業にいては経験できないとても楽しみな時間でした。この時間のおかげで、分野を横断する複合領域を見る目が涵養されたのではないかと思います。いろいろと学べて、楽しめて、大変でしたがとても貴重な3年間でした。
ここで学んだものは科研費のことだけではありません。私の所属した工学/総合班には、工学とその境界領域の各分野で日本を代表する先生方が集まっておられます。毎月の会議で先生方からそれぞれの分野の最先端の話を聞かせていただけるのですが、これが初めて聞く刺激的なものばかりで、企業にいては経験できないとても楽しみな時間でした。この時間のおかげで、分野を横断する複合領域を見る目が涵養されたのではないかと思います。いろいろと学べて、楽しめて、大変でしたがとても貴重な3年間でした。
(『学術システム研究センターリーフレット2017』2017年4月より)
出会いは、 知的好奇心の源泉

河野 勝
早稲田大学
政治経済学術院教授
社会科学専門調査班主任研究員(平成25年4月~平成28年3月)
政治経済学術院教授
社会科学専門調査班主任研究員(平成25年4月~平成28年3月)
主任研究員は、科研費の審査制度の運営等に関わる「プログラムオフィサー」としての顔をもつ一方で、「研究員」でもあり、それぞれ学術の動向について調査研究を行っている。その一環として、私の場合は、ふだんでは参加しないような学会や研究会に大手を振ってお邪魔することがあるのだが、これが結構楽しい。見聞を広げられるだけでなく、外側から自分の専門分野の学術的特徴を考え直す良い機会を提供してくれている。
隔週で開かれる主任研究員会議では、振興会のさまざまな活動や運営についての議論が交わされる。その冒頭では、輪番で主任研究員が自分の研究を発表する時間が設けられている。各方面の第一線で研究なさっている方々の、まさに一番得意とするお話しを直接うかがうことができるわけで、毎回知的興奮を覚えずにはいられない。
歳をとると、人間だれでも新しい物事への関心や興味が減退するものであるが、その傾向に抗する最良の方法は魅力ある人と出会うことだと、私は常々思っている。人生の折り返し地点を過ぎた身でありながら、このセンターでの活動を通して、多くの魅力ある人々と新たに知己を得ることができたのは、私にとってこの上ない幸せである。
隔週で開かれる主任研究員会議では、振興会のさまざまな活動や運営についての議論が交わされる。その冒頭では、輪番で主任研究員が自分の研究を発表する時間が設けられている。各方面の第一線で研究なさっている方々の、まさに一番得意とするお話しを直接うかがうことができるわけで、毎回知的興奮を覚えずにはいられない。
歳をとると、人間だれでも新しい物事への関心や興味が減退するものであるが、その傾向に抗する最良の方法は魅力ある人と出会うことだと、私は常々思っている。人生の折り返し地点を過ぎた身でありながら、このセンターでの活動を通して、多くの魅力ある人々と新たに知己を得ることができたのは、私にとってこの上ない幸せである。
(『学術システム研究センターリーフレット2015』2015年9月より)
科学者自身が守る科研費

長谷部 光泰
自然科学研究機構
基礎生物学研究所教授
生物系科学専門調査班主任研究員(平成25年4月~平成28年3月)
基礎生物学研究所教授
生物系科学専門調査班主任研究員(平成25年4月~平成28年3月)
科研費は研究者の命の水です。しかし、研究者は文科省の研究者ではない官僚に自分たちの命運をゆだね、自力で自らの命を守ることができないのだと思っていました。しかし、官僚と研究者をメルティングポットに入れて昇華させ、日本の科学をより良くしていこうという組織があることを知りました。それが学術システム研究センターです。センター職員は、研究者が階級も時空をも超えて自由な発想で学術研究ができるような仕組みを作ろう、そんな高邁な思想のもと、科学者たちの無理難題に現実味を持たせてくれます。理想と現実のギャップはどんどん縮まっているように思います。この3 年間、恒例の審査員選考と審査結果の検証に加え、系分野分科細目表の見直し、新二段階審査方式の検討、新分野創成の呼び水としての特設分野設定、重複受給の可否などなど、ずいぶんたくさんの仕事に関わらせていただきましたが、その実現性の高さは苦労をふきとばすものでした。研究者が自らの研究がしやすいように、自分たちの手でどんどん制度を良くできる。心地良い疲れと充実感、一生に一度で良いですが、なんともやりがいのある仕事でした。
(『学術システム研究センターリーフレット2016』2016年4月より)
若手研究者の育成と学術システム研究センター

窪田 幸子
神戸大学大学院
国際文化学研究科教授
人文学専門調査班専門研究員(平成25年4月~平成28年3月)
国際文化学研究科教授
人文学専門調査班専門研究員(平成25年4月~平成28年3月)
学術システム研究センター専門研究員としての3年間は、予想以上に大変でした! しかし、終わってみるとあっという間で、とても楽しい時間でした。最初は、何をどうすればよいのか戸惑ってばかりでしたが、人文社会班の多彩な主任研究員、専門研究員の皆様との意見交換が大変面白く、センターに行くことが次第に楽しみになっていました。そして科学研究費に関わる様々な仕事をこなすなかで、組織の仕組みが次第に分かり、このセンターの役割の大きさと重要性が理解できたように思います。
専門研究員としての大きな仕事の一つに日本学術振興会賞の予備審査があります。毎年夏休み前に担当する45 歳未満の候補者たちの全業績が届きます。業績全てを対象とする査読なので、候補者の研究内容に細かく接することとなり、結果として若手の研究の面白さと問題点が見えます。専門研究員の仕事の中では、このように、日本学術振興会賞の予備審査、特別研究員事業など、若手研究者の育成にかかわることも重要な位置を占めています。任期の3 年間を通じ、日本の学術の現在と将来を支えるシステムが健全に保たれていることが何よりも枢要であることを実感し、その運用に微力ながらもかかわれたことを嬉しく思っています。
専門研究員としての大きな仕事の一つに日本学術振興会賞の予備審査があります。毎年夏休み前に担当する45 歳未満の候補者たちの全業績が届きます。業績全てを対象とする査読なので、候補者の研究内容に細かく接することとなり、結果として若手の研究の面白さと問題点が見えます。専門研究員の仕事の中では、このように、日本学術振興会賞の予備審査、特別研究員事業など、若手研究者の育成にかかわることも重要な位置を占めています。任期の3 年間を通じ、日本の学術の現在と将来を支えるシステムが健全に保たれていることが何よりも枢要であることを実感し、その運用に微力ながらもかかわれたことを嬉しく思っています。
(『学術システム研究センターリーフレット2016』2016年4月より)
正当性と公平性を保つために

伊原 博隆
熊本大学大学院
自然科学研究科教授
化学専門調査班専門研究員(平成25年4月~平成28年3月)
自然科学研究科教授
化学専門調査班専門研究員(平成25年4月~平成28年3月)
多くの専門研究員の方が、業務をスタートさせて感じられるであろうことは、現在の科研費システムが、審査の正当性や公平性を保つために機能するよう設計されているということ、そして、このシステムを維持・改善するために、専門研究員と職員が一体となり、使命感をもって粛々と作業を進めていく感覚ではないかと推察いたします。また、現在のシステムに至るまでには、信念と情熱をもって改革に挑んだ方々がおられたに違いないであろうことも、容易に類推できます。これが専門研究員となった私の第一印象であって、一年経った今でも、その印象は変わりません。
私自身、アカデミアの一員となって以来、主な競争的外部資金は日本学術振興会の科研費であり、時には審査システムに不安を抱いた時期もありましたが、審査システムの全体像に触れるにつれ、この不安感はほぼ解消され、むしろ、採択に至った課題が、学術性や新規性、実現性等に対して一定の評価がなされたものと確信するに至りました。人が審査する以上、そこには期待を裏切る結末が待っていることもあります。しかし、私は専門研究員の一人として、今後も正当性と公平性を保つために、また科研費のあるべき道に対して少しでもお役に立てるメッセージを残していきたいと思っています。
私自身、アカデミアの一員となって以来、主な競争的外部資金は日本学術振興会の科研費であり、時には審査システムに不安を抱いた時期もありましたが、審査システムの全体像に触れるにつれ、この不安感はほぼ解消され、むしろ、採択に至った課題が、学術性や新規性、実現性等に対して一定の評価がなされたものと確信するに至りました。人が審査する以上、そこには期待を裏切る結末が待っていることもあります。しかし、私は専門研究員の一人として、今後も正当性と公平性を保つために、また科研費のあるべき道に対して少しでもお役に立てるメッセージを残していきたいと思っています。
(『学術システム研究センターリーフレット2015』2015年9月より)
志のある研究者を育てる志

長坂 雄次
慶應義塾大学
理工学部教授
工学系科学専門調査班主任研究員(平成24年4月~平成27年3月)
理工学部教授
工学系科学専門調査班主任研究員(平成24年4月~平成27年3月)
日本の学術を取り巻く環境は大きく変化している。科学研究費のような学術研究の財政的支援についてはもちろんだが、次を担う若手研究者の就職に対しても強い逆風が吹いていると言っても言い過ぎではないだろう。最近はアカデミックポストに就くことは難しい時代になった。理由は大学等におけるポストの減少、そしてそれとは逆に競争的資金による任期付ポスドク雇用の増加等である。限られた財源の中でより優れた研究や研究者を支援するには、競争的であることは必要条件である。優れた資質のある芽を見出し優れた若手研究者に育て上げるためには、良い研究環境や一定の競争的環境は重要である。しかし、それだけで日本の学術を真に牽引する人材が育つだろうか。研究環境が少し悪くなったり研究資金が獲得できないと、すぐに自分の自由な発想による学術研究を放棄してしまう人がいるとしたら、足りなかったものは「志」だろうと私は思う。特別研究員制度(DC、PD 等)は、若手研究者(の卵)が自らの発想と研究意欲をもとに、独立した研究者として成長するための支援である。つまり研究者としての「志」を育てることも暗黙の使命なのである。今後も志のある研究者を育てる志をもった研究員の皆様の熱い議論で、より良い制度設計を進めて頂ければと願っている。
(『学術システム研究センターリーフレット2016』2016年4月より)
日本の未来を支える基礎研究とそれを支えるもの

吉田 稔
理化学研究所
主任研究員
農学専門調査班主任研究員(平成24年4月~平成27年3月)
主任研究員
農学専門調査班主任研究員(平成24年4月~平成27年3月)
ここ数年、毎年ノーベル賞ウィークに日本は沸いています。日本人の受賞は、日本の科学技術や文化レベルの高さを示すものとして、国民の誰もが喜びを感じているのでしょう。日本には多くの潜在的候補者がいると言われ、今後も受賞が期待されます。しかし、研究の開始から30年以上もの間の地道な研究活動の末に受賞となる例がほとんどであり、日本の成功は、若い研究者の荒唐無稽と思われるような自由な発想の基礎研究を継続的に支援できる環境を作ってきた先人達のおかげであると言っても過言ではないのです。しかし、国の財政難の中、これを維持し、発展させるのは決して容易なことではありません。学術システム研究センターの主任研究員となった私は、科研費や特別研究員制度について常に危機感をもって制度や運用の改革を議論する皆さんの姿に驚きと尊敬の念を覚えました。生来議論好きの私は、すっかりそれにのめり込んでしまい、あっという間の任期3年でした。きっと多くの研究員が同じような気持ちで、日本の未来のあるべき姿を思い描いているのだと思います。今から30年、40年後のノーベル賞ウィークでも日本が沸き立っていることを願ってやみません。そうなっていたら、学術システム研究センターにも少しだけ拍手を送ってあげてください。
(『学術システム研究センターリーフレット2017』2017年4月より)
すべては、創造的な研究のために

平井 みどり
神戸大学
医学部附属病院教授
医歯薬学専門調査班専門研究員(平成24年4月~平成27年3月)
医学部附属病院教授
医歯薬学専門調査班専門研究員(平成24年4月~平成27年3月)
毎年、秋になると気ぜわしいのは、科研費の申請書類を作成する時期に当たるからである。今でこそ電子申請が当たり前になっているが、以前は書類の切り貼り、コピーと糊付け作業、マジックで角に色づけなど、なんでこんなに面倒な事しなきゃいけないの? などとブツブツ文句を言いながら、締め切りギリギリに事務の方々の視線を背中に痛く感じつつ作業していた。
自分自身、もっぱら申請する側であったのが、あるとき巨大な段ボールが送られてきて、書面審査せよといわれ、ええーっ、こんなに沢山! と、涙のお正月を何年か過ごした。その後、思いがけず研究員にご指名を頂き、気がつけば2年が過ぎようとしている。研究員になって初めて知ることができたのは、科研費はピアレビューとして、非常にしっかりしたシステムであるということと、研究員の先生方は、オフィシャルな場でお見かけするよりもずっと面白い、ということである。科研費は研究者の自由度が(今のところはまだ)高く、本当に有り難い助成である。研究のアクティビティと創造性のために、ピアレビューのシステムを守り続けるのが我々の使命だ。そのために、あらゆる面で支えて下さる事務担当の皆様への感謝を、ゆめゆめ忘れないようにしなければならない。
自分自身、もっぱら申請する側であったのが、あるとき巨大な段ボールが送られてきて、書面審査せよといわれ、ええーっ、こんなに沢山! と、涙のお正月を何年か過ごした。その後、思いがけず研究員にご指名を頂き、気がつけば2年が過ぎようとしている。研究員になって初めて知ることができたのは、科研費はピアレビューとして、非常にしっかりしたシステムであるということと、研究員の先生方は、オフィシャルな場でお見かけするよりもずっと面白い、ということである。科研費は研究者の自由度が(今のところはまだ)高く、本当に有り難い助成である。研究のアクティビティと創造性のために、ピアレビューのシステムを守り続けるのが我々の使命だ。そのために、あらゆる面で支えて下さる事務担当の皆様への感謝を、ゆめゆめ忘れないようにしなければならない。
(『学術システム研究センターリーフレット2015』2015年9月より)
基盤形成のマネジメントとは?

射場 英紀
トヨタ自動車株式会社
電池研究部長
総合系専門調査班専門研究員(平成23年10月~平成26年3月)
電池研究部長
総合系専門調査班専門研究員(平成23年10月~平成26年3月)
まずは、学術システム研究センターの皆様、先生方にはたいへんお世話になりました。本当にありがとうございました。民間企業のマネージャーの小職にはいろいろ驚くことが多く、有意義な期間を過ごすことができました。
専門研究員を経験する中でいちばんの驚きは、科研費や特別研究員の審査のためのしくみが、客観的で公正な審査結果をひきだすために、いかに多くの工夫がなされているかということでした。また、そのしくみの中で、審査員の先生方が、膨大な申請の中から一件でもよりよい研究を採択できるよう熱心に議論される光景も印象的でした。
今期の科学技術基本計画においては、イノベーションを加速する施策が数多く立案されていますが、これらを構成する研究開発テーマは、すべて科研費による「基盤研究」に原点があるといっても過言ではないと思います。そしてそのひとつの研究シーズやひとりの研究人材を丁寧に育てていくために、この学術振興会のマネジメントのしくみが、よく機能していることを感じとることができました。私自身、今後は、この期間の経験を活かして、特に基盤研究のフェーズから、イノベーションにつながる開発フェーズへ移行していく部分を、加速するようなしくみを模索していきたいと思います。
専門研究員を経験する中でいちばんの驚きは、科研費や特別研究員の審査のためのしくみが、客観的で公正な審査結果をひきだすために、いかに多くの工夫がなされているかということでした。また、そのしくみの中で、審査員の先生方が、膨大な申請の中から一件でもよりよい研究を採択できるよう熱心に議論される光景も印象的でした。
今期の科学技術基本計画においては、イノベーションを加速する施策が数多く立案されていますが、これらを構成する研究開発テーマは、すべて科研費による「基盤研究」に原点があるといっても過言ではないと思います。そしてそのひとつの研究シーズやひとりの研究人材を丁寧に育てていくために、この学術振興会のマネジメントのしくみが、よく機能していることを感じとることができました。私自身、今後は、この期間の経験を活かして、特に基盤研究のフェーズから、イノベーションにつながる開発フェーズへ移行していく部分を、加速するようなしくみを模索していきたいと思います。
(『学術システム研究センターリーフレット2015』2015年9月より)
