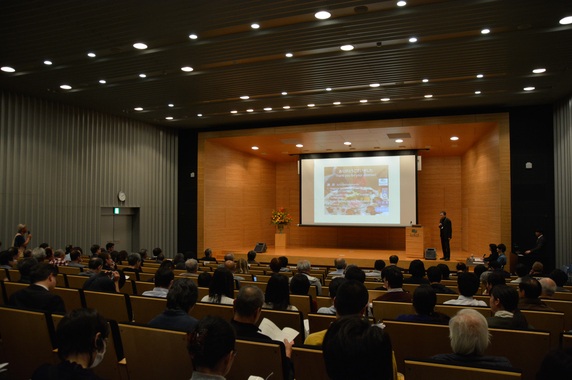国際生物学賞
International Prize for Biology第34回授賞式・受賞者あいさつ・審査経過報告
天皇皇后両陛下のご臨席を仰いで、
第34回国際生物学賞授賞式が挙行されました。
(平成30年11月19日)
第34回国際生物学賞授賞式が挙行されました。
(平成30年11月19日)

第34回国際生物学賞授賞式は、11月19日に日本学士院において、天皇皇后両陛下のご臨席を仰ぎ、内閣総理大臣代理として左藤章内閣府副大臣、柴山昌彦文部科学大臣をはじめ、各界から多数の来賓の参列を得て、盛会のうちに執り行われました。
式典では、井村裕夫国際生物学賞委員長から、受賞者のアンドリュー・ハーバート・ノール博士に、賞状と賞金1,000万円及び賞牌が授与され、天皇陛下からの賜品「御紋付銀花瓶」が伝達されました。
続いて、内閣総理大臣祝辞(代読 左藤章内閣府副大臣)、並びに文部科学大臣祝辞の後、ノール博士が受賞の挨拶を行いました。
引き続き、天皇皇后両陛下ご臨席の下、受賞者を囲んで記念茶会が行われました。
式典では、井村裕夫国際生物学賞委員長から、受賞者のアンドリュー・ハーバート・ノール博士に、賞状と賞金1,000万円及び賞牌が授与され、天皇陛下からの賜品「御紋付銀花瓶」が伝達されました。
続いて、内閣総理大臣祝辞(代読 左藤章内閣府副大臣)、並びに文部科学大臣祝辞の後、ノール博士が受賞の挨拶を行いました。
引き続き、天皇皇后両陛下ご臨席の下、受賞者を囲んで記念茶会が行われました。

賜品を手にするノール博士夫妻

記念茶会
アンドリュー・ハーバート・ノール 博士

今、私は大きな喜びとともに恐縮の思いを抱きながら、皆様の前に立っております。大きな喜びとは、仲間である研究者たちからこのような栄誉ある賞に推薦されたことによるものであり、また恐縮の思いとは、悠久の生命史の再構築に日々取り組んでおられる優秀な研究者を置いて私が選ばれたことによるものであります。
本日は天皇皇后両陛下の御臨席を賜わり、誠に喜びに堪えません。両陛下が基礎生物学に変わらぬご支援をお寄せくださることに心から感謝申し上げます。長年にわたる昭和天皇の海洋生物学の御研究、そして今上天皇のハゼ類の御研究と、皇室のみなさまは生物学に御理解をお示しくださるだけでなく、御自身もまた自然の探求に御心を注がれていらっしゃいます。これは素晴らしいことと存じます。この度の受賞にあたりましては、生物学研究・教育を力強く支援してこられた日本学術振興会にも御礼申し上げます。
本日私がいる、この特別な場所に到達する研究者は、概して2つの知的な流れの合流点に立っていると言えます。その1つは私たちの師から注がれた流れです。私の師は、地球上の初期の生命に関する古生物学的研究の先駆者であるエルソ・バーフォーン教授、優れた地球化学者として地球環境史研究の礎を築いたディック・ホランド教授、そして、私が進化への関心に目覚めるきっかけを作ってくださったスティーヴン・ジェイ・グールド教授です。もう1つの流れは、私たち研究者と研究室に所属していた学生・博士研究員とを結びつける流れです。彼らとの交流は、絶えずさまざまな考えや洞察をもたらします。ノール研究室の同窓生はみな素晴らしい研究者たちばかりです。古生物学、地球生物学、地球史研究で新たな方向性を導き出しています。彼らに感謝すると同時に、彼らは私の誇りでもあります。ともに研究に励んだ仲間たちからも実に多くのものを得ました。その中から、私の生物地球化学に関する知識の源であるジョン・ヘイズ教授、私を北極研究へと導いてくれたキーン・スウェット、ブライアン・ハーランドの両教授、この25年間ナミビア、シベリアに始まり、仮想空間上ではありますが火星に至るまで、野外観察を一緒に行ってきたジョン・グロッチンガー教授、そして、新たな方向性を求めて長年議論を交わしてきたディック・バンバック教授のお名前をここでは挙げたいと思います。最後に、妻のマーシャと二人の子どもたち、カースティンとロブに感謝の気持ちを捧げます。彼らの愛情と支えなくして、今日私がこの場にいることはなかったでしょう。
国際生物学賞という栄誉を与えられた基礎生物学は、ひとつの壮大な問いに取り組んでいます。それは、私たちの世界はどのように出現したのか、ということです。この問いはある部分、過程の問題であり、国際生物学賞が生態系、進化、遺伝に関する研究を表彰なさっていることは当然のことと言えます。しかし、同時にこの問いは歴史の問題でもあり、この点において、古生物学がこの特色ある賞の授賞対象分野となっていることに深く感謝したいと存じます。古生物学の研究がなかったなら、恐竜がかつて存在していたことなど私たちは考えも及ばなかったでしょう。ましてやその恐竜たちが今は絶滅してしまった植物の生い茂る森林で私たちが見たこともないような姿の哺乳類と共存していたこと、恐竜をはじめ無数の種が6,600万年前の小惑星衝突により死に絶えたことなど、まず知る由もなかったでしょう。
古生物学とは、私たちの発見した化石が地球のダイナミックな環境史の枠組みの中で解釈されることであると私は考えます。実際、生命というのは地球上で起きる現象であり、地球史の過程によって生じ、維持されるものです。そして年月を経て、生命それ自体が重要な一連の過程となります。生命と環境との深く絶えず変化する相互関係は、進化を、また地球という天体そのものを形成してきました。この壮大な相互作用を探求することは、私たち人間がどこから来て、この先、21世紀の地球変動に直面する中でどこに向かう可能性があるのかを理解する助けとなることでしょう。
格別の栄誉を賜りましたことに、あらためて御礼申し上げます。
本日は天皇皇后両陛下の御臨席を賜わり、誠に喜びに堪えません。両陛下が基礎生物学に変わらぬご支援をお寄せくださることに心から感謝申し上げます。長年にわたる昭和天皇の海洋生物学の御研究、そして今上天皇のハゼ類の御研究と、皇室のみなさまは生物学に御理解をお示しくださるだけでなく、御自身もまた自然の探求に御心を注がれていらっしゃいます。これは素晴らしいことと存じます。この度の受賞にあたりましては、生物学研究・教育を力強く支援してこられた日本学術振興会にも御礼申し上げます。
本日私がいる、この特別な場所に到達する研究者は、概して2つの知的な流れの合流点に立っていると言えます。その1つは私たちの師から注がれた流れです。私の師は、地球上の初期の生命に関する古生物学的研究の先駆者であるエルソ・バーフォーン教授、優れた地球化学者として地球環境史研究の礎を築いたディック・ホランド教授、そして、私が進化への関心に目覚めるきっかけを作ってくださったスティーヴン・ジェイ・グールド教授です。もう1つの流れは、私たち研究者と研究室に所属していた学生・博士研究員とを結びつける流れです。彼らとの交流は、絶えずさまざまな考えや洞察をもたらします。ノール研究室の同窓生はみな素晴らしい研究者たちばかりです。古生物学、地球生物学、地球史研究で新たな方向性を導き出しています。彼らに感謝すると同時に、彼らは私の誇りでもあります。ともに研究に励んだ仲間たちからも実に多くのものを得ました。その中から、私の生物地球化学に関する知識の源であるジョン・ヘイズ教授、私を北極研究へと導いてくれたキーン・スウェット、ブライアン・ハーランドの両教授、この25年間ナミビア、シベリアに始まり、仮想空間上ではありますが火星に至るまで、野外観察を一緒に行ってきたジョン・グロッチンガー教授、そして、新たな方向性を求めて長年議論を交わしてきたディック・バンバック教授のお名前をここでは挙げたいと思います。最後に、妻のマーシャと二人の子どもたち、カースティンとロブに感謝の気持ちを捧げます。彼らの愛情と支えなくして、今日私がこの場にいることはなかったでしょう。
国際生物学賞という栄誉を与えられた基礎生物学は、ひとつの壮大な問いに取り組んでいます。それは、私たちの世界はどのように出現したのか、ということです。この問いはある部分、過程の問題であり、国際生物学賞が生態系、進化、遺伝に関する研究を表彰なさっていることは当然のことと言えます。しかし、同時にこの問いは歴史の問題でもあり、この点において、古生物学がこの特色ある賞の授賞対象分野となっていることに深く感謝したいと存じます。古生物学の研究がなかったなら、恐竜がかつて存在していたことなど私たちは考えも及ばなかったでしょう。ましてやその恐竜たちが今は絶滅してしまった植物の生い茂る森林で私たちが見たこともないような姿の哺乳類と共存していたこと、恐竜をはじめ無数の種が6,600万年前の小惑星衝突により死に絶えたことなど、まず知る由もなかったでしょう。
古生物学とは、私たちの発見した化石が地球のダイナミックな環境史の枠組みの中で解釈されることであると私は考えます。実際、生命というのは地球上で起きる現象であり、地球史の過程によって生じ、維持されるものです。そして年月を経て、生命それ自体が重要な一連の過程となります。生命と環境との深く絶えず変化する相互関係は、進化を、また地球という天体そのものを形成してきました。この壮大な相互作用を探求することは、私たち人間がどこから来て、この先、21世紀の地球変動に直面する中でどこに向かう可能性があるのかを理解する助けとなることでしょう。
格別の栄誉を賜りましたことに、あらためて御礼申し上げます。
国際生物学賞審査委員会委員長 阿形 清和

第34回国際生物学賞審査委員会を代表いたしまして、今回の審査の経緯について御報告申し上げます。
審査委員会は、私及び海外の研究者3名を含む19名の委員で構成いたしました。
審査委員会は、今回の授賞対象分野である「古生物学」にふさわしい受賞者を推薦いただくため、国内外の大学、研究機関、学協会および国際学術団体等に、1,555通の推薦依頼状を送りました。その結果、85通の推薦状が届きました。
このうち重複を除いた被推薦者の数は19か国・地域の56名でございました。
審査委員会は、3回の会議を開催して、慎重に候補者の選考を行い、第34回国際生物学賞受賞者として、アンドリュー・ハーバート・ノール博士を国際生物学賞委員会へ推薦いたしました。ノール博士は、ハーバード大学で博士号を取得後、オーバリン大学やハーバード大学で研究を続けられ、現在はハーバード大学 自然史学 フィッシャー記念教授として研究・教育にあたられております。
ノール博士は、初期の地球上の環境とその変化に基づいた微化石の研究により、生物についての情報が極めて乏しいカンブリア紀以前の生命進化の理解に大きく寄与されたほか、大気中の急速な二酸化炭素の蓄積が顕生代ペルム紀末に植物や動物の大量絶滅をもたらしたという仮説を立て、その進化の歴史を理解することに貢献されました。これらは地球生命の今後を予測する上でも重要な知見を与えるもので、その功績は高く評価されています。さらにノール博士は最近の10年間、NASAの火星探査プロジェクトに加わってその研究計画と実践を牽引され、初期の地球生命に関する知見を用いて火星の生命と環境に関する研究にも貢献されています。
ノール博士の業績は、本賞の審査基準である、授賞対象分野への適合性、研究の独創性、当該分野における影響力、および生物学全般への貢献度のいずれをも十分に満たすものであります。 国際生物学賞委員会は、審査委員会の推薦に基づいて審議を行い、アンドリュー・ハーバート・ノール博士に対し、第34回国際生物学賞を授与することを決定いたしました。
以上をもちまして、私の審査経過報告と致します。
審査委員会は、私及び海外の研究者3名を含む19名の委員で構成いたしました。
審査委員会は、今回の授賞対象分野である「古生物学」にふさわしい受賞者を推薦いただくため、国内外の大学、研究機関、学協会および国際学術団体等に、1,555通の推薦依頼状を送りました。その結果、85通の推薦状が届きました。
このうち重複を除いた被推薦者の数は19か国・地域の56名でございました。
審査委員会は、3回の会議を開催して、慎重に候補者の選考を行い、第34回国際生物学賞受賞者として、アンドリュー・ハーバート・ノール博士を国際生物学賞委員会へ推薦いたしました。ノール博士は、ハーバード大学で博士号を取得後、オーバリン大学やハーバード大学で研究を続けられ、現在はハーバード大学 自然史学 フィッシャー記念教授として研究・教育にあたられております。
ノール博士は、初期の地球上の環境とその変化に基づいた微化石の研究により、生物についての情報が極めて乏しいカンブリア紀以前の生命進化の理解に大きく寄与されたほか、大気中の急速な二酸化炭素の蓄積が顕生代ペルム紀末に植物や動物の大量絶滅をもたらしたという仮説を立て、その進化の歴史を理解することに貢献されました。これらは地球生命の今後を予測する上でも重要な知見を与えるもので、その功績は高く評価されています。さらにノール博士は最近の10年間、NASAの火星探査プロジェクトに加わってその研究計画と実践を牽引され、初期の地球生命に関する知見を用いて火星の生命と環境に関する研究にも貢献されています。
ノール博士の業績は、本賞の審査基準である、授賞対象分野への適合性、研究の独創性、当該分野における影響力、および生物学全般への貢献度のいずれをも十分に満たすものであります。 国際生物学賞委員会は、審査委員会の推薦に基づいて審議を行い、アンドリュー・ハーバート・ノール博士に対し、第34回国際生物学賞を授与することを決定いたしました。
以上をもちまして、私の審査経過報告と致します。
受賞を記念して、名古屋大学、日本学術振興会の共催により第34回国際生物学賞記念シンポジウム「初期生命の進化」が11月21日(水)、22日(木)の2日間、名古屋大学 野依記念学術交流館にて開催されました。
受賞者のノール博士による特別講演をはじめ、国内外の研究者が、古生物学に関する最新の研究成果についての講演を行いました。
受賞者のノール博士による特別講演をはじめ、国内外の研究者が、古生物学に関する最新の研究成果についての講演を行いました。